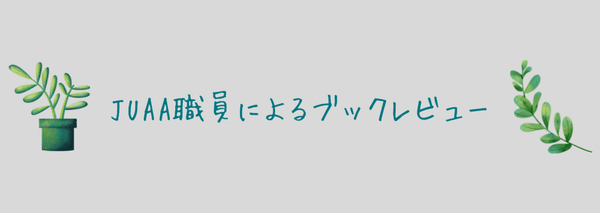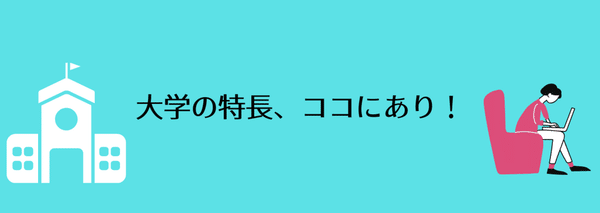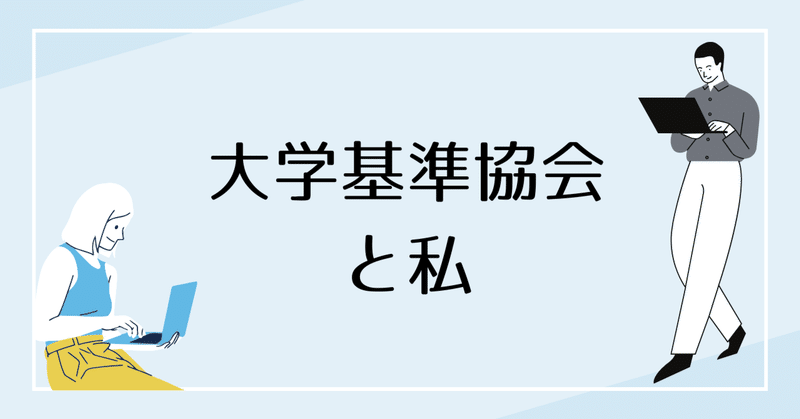大学基準協会公式note
大学の評価を行っている公益財団法人大学基準協会の公式アカウントです。「もっと身近に」「もっとわかりやすく」をモットーに、大学のことや私たちの取組み等を発信していきたいと思います。
大学基準協会と私
大学基準協会で役員や委員会委員を務めた方や、研修修了者等で本協会の活動に長く関わる方に、これまでの仕事を振り返りながら、本協会の活動の意義や期待することなどについて執筆していただきます。
1000分の1の出会いのために
数多ある大学の中から、将来を夢見ながら、興味・関心や条件などで志望校を選んでいく。それは、輝かしい大学生活に向けた「はじめの一歩」である…このマガジンでは、大学の裏側にも迫りながら、受験生の「大学選び」のヒントとなる様々な情報をお伝えしていきます。受験生以外の方にも、イマドキの大学選びについて考えるきっかけになれば幸いです。

岐阜聖徳学園大学における体験型教員養成プロジェクト「クリスタルプラン」を通じた教職教育|大学の特長、ココにあり!#19
今回取材する取組みについて本協会の大学評価では、以下のように評価し、「長所」として取り上げています。 岐阜聖徳学園大学の設立と教育理念について――はじめに、貴大学の設立の背景や経緯などについて教えてください。 秋山(敬称略):本学は、1972年に聖徳学園岐阜教育大学として創立されました。戦後の高度成長期において、「人を育てる」営み、すなわち教育学部を有する大学の設立に向けて、岐阜を中心とした仏教界の方々が動かれたという話を聞いております。設立当初は、教育学部のみの単科大学
スキ
18
3分で知る!大学の今
社会や経済が急激に変化する中で、大学における教育研究のあり方も大きく変化しています。「3分で知る!大学の今」と題した本マガジンでは、評価を通じて多くの大学を見て来た大学基準協会職員が、変化する大学の「今」をわかりやすくお伝えしていきます。