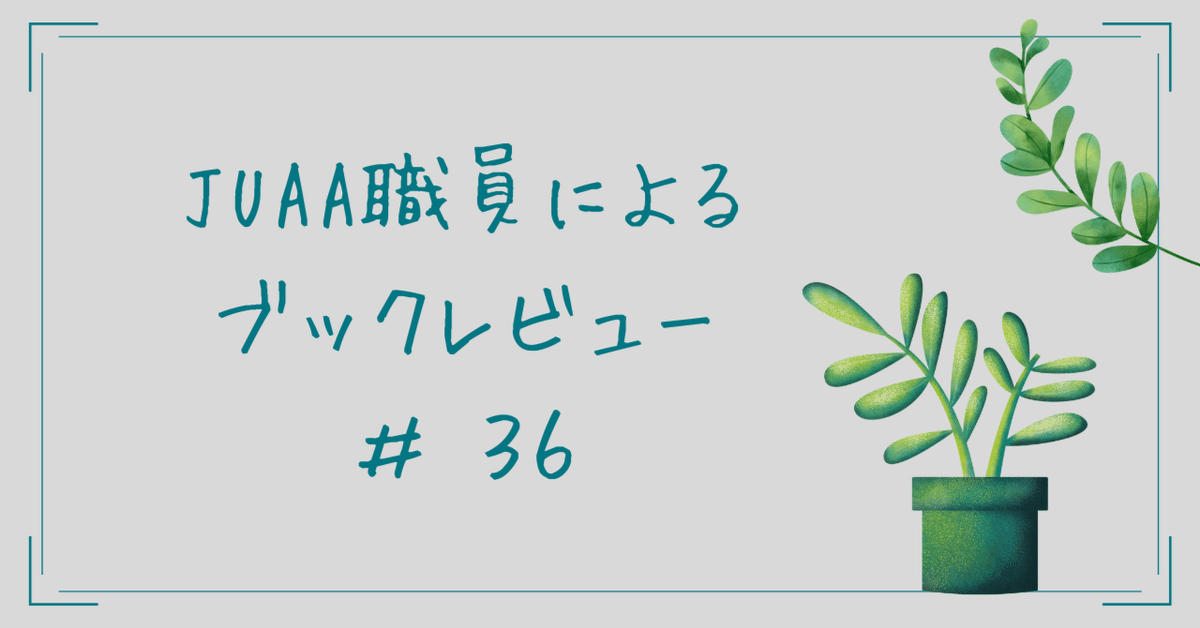
『大学はもう死んでいる? トップユニバーシティーからの問題提起』【ブックレビュー#36】
このコーナーでは、大学基準協会職員が自らの興味・関心に基づく書籍等を紹介しつつ、それぞれが考えたことや感じたことを自由に発信していきます。大学の第三者評価機関に勤める職員の素顔を少しでも知っていただけたら幸いです。なお、掲載内容はあくまで職員個人の見解であり、大学基準協会の公式見解ではありません。
評価事業部評価第1課の山越です。
2度目のブックレビューを書くこととなり、なるべく読みやすそうで、かつ面白そうな本にしたいと思い、本協会の書庫に立ち寄って手に取った本がこちらです。
苅谷剛彦、吉見俊哉『大学はもう死んでいる? トップユニバーシティーからの問題提起』集英社新書、2020年
本書の構成
これまで本協会が行ってきたブックレビューにおいて、苅谷先生の著書は第9回と第28回でも取り上げています。
今回私が選んだこの本は、オックスフォード大学教授の苅谷先生と、東京大学に所属し、ハーバード大学でも教鞭をとったご経験を有する吉見先生の対談形式で展開されます。
本書は全6章で構成されており、各章において「大学改革」「授業」「職員」「文系と理系」「グローバル化」「キャンパス」といったキーワードから、オックスフォード等の世界におけるトップ大学と日本におけるトップレベルの大学の比較を通じて、日本の大学が抱える問題について論じています。
本書の「はじめに」において、吉見先生は次のように述べています。
要するに、日本の大学は二重の意味で「もう死んでいる」のかもしれないのであり、問題の根は、一般に考えられているよりはるかに深いのだ。この日本の大学の絶望的な谷間から脱出する方法は簡単ではない。逆転スリーランのような決定打があるわけではないからだ。
日本の大学教育の課題
大学で行う学部教育の多くは4年間で所定の単位数を取得してしまえば卒業ができるので、単純に大学というものを考えると、4年間を一つの区切りとして、それが繰り返されて連続していくようなイメージで捉える方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、実際には大学で行う教育研究は決して4年間という短期で区切れるようなものではなく、長い歴史を土台としながら、長期的かつ永続的に発展し続けていくものです。
そもそも教育というのはその成果を商品のように可視化することが難しく、そして、その成果は社会に出てすぐに表出したり、実感したりすることはほとんどできないように思います。
大学教育の課題についても同様です。なので、社会が大学を「もう死んでいる」と判断した頃には既に手遅れなのかもしれません。そして、その理由の根幹は、想像するよりも過去にある、ということとなります。
「はじめに」で語られるように、本書のタイトル『大学はもう死んでいる?』にはクエスチョンマークがついており、
大学がもう死んでいるのか、それともまだ死んではいないのか、答えは確定していない。
ことが述べられ、6章を通じて、大学が直面している課題や危機にどう対応していくべきかというヒントが示されています。
文理融合から文理複眼へ
さて、6つの章は先ほど述べたようにそれぞれキーワードをもって日本の大学の課題とオックスフォード大学の事例が語られていきますが、その中でも私が一番興味深く感じたのは、「文系と理系」をキーワードとして扱う第4章「分離融合から分離複眼へ」です。
私が大学基準協会に入職する前年に、「文系学部廃止論」がマスコミを通じて話題となり、当時文系学部に所属していた私自身これからどうなるのだろうといった不安や自分の学んでいる学問が不要といわれているようなある種のショックを感じた記憶があります。
その後も定期的に「果たして文系は社会の役に立つのか」といった論争がSNS等を通じておこるのを目にすることがありますが、この問いに対し、吉見先生は次のように提示しています。
「役に立つ」ということには二種類あって、既に与えられている目的に対して手段として役に立つだけがすべてではありません。こういう目的遂行的、あるいは手段的な有用性とは別に、価値を創造することで役に立つという次元があります。
手段的な「役に立つ」ということの中からは、歴史の転換期に新しい社会の目的や価値の軸を創造することはけっして出てきません。(中略)これはつまり、方法化された想像力を用いて違う価値とどう交渉し、対話するかという作業であり、まさに文系の学問が常にやっていることです。
新しい価値創造がいかに大切かということがわかっていれば、文系が役に立たないなんていうことは絶対に言えないはずです。
このことは、「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」(2018年)において予測不可能な時代に必要とされる人材像として示される、「普遍的な知識・理解と汎用的技能を文理横断的に身に付け」「時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、論理的思考力を持って社会を改善していく資質を有する人材」にもつながるものだと思います。
終わりに
つらつらと書き連ねてきましたが、最後に本書の「おわりに」の一文を紹介したいと思います。
大学を死なせてはならない。そのために何が必要か。それを考え、行動に移す手がかりが本書には含まれているはずだ。そしてその手がかりが、新たな知の交流を生み出していくことを望んで止まない。それを求める人々がいる限り、大学は簡単には死なない。

