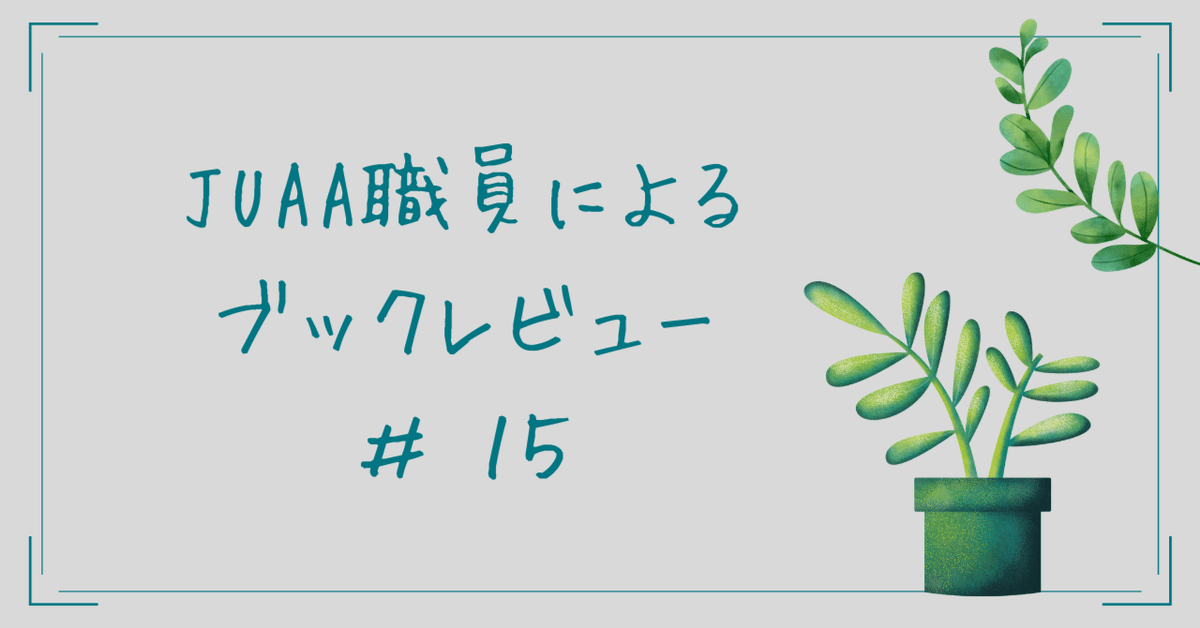
JUAA職員によるブックレビュー#15
このコーナーでは、大学基準協会職員が自らの興味・関心に基づく書籍等を紹介しつつ、それぞれが考えたことや感じたことを自由に発信していきます。大学の第三者評価機関に勤める職員の素顔を少しでも知っていただけたら幸いです。なお、掲載内容はあくまで職員個人の見解であり、大学基準協会の公式見解ではありません。
評価事業部評価第1課の佐藤(圭)です。主に大学と短期大学の認証評価に係る業務に従事しています。
私には子どもがおり、小学校入学も視野に入ってきました。そんななか、高等教育のみならず初等・中等教育に関する多角的な視座からの論考を収めたこの本を手に取りました。
松岡亮二編著『教育論の新常識―格差・学力・政策・未来』中央公論新社、2021年
本書の編著者は、膨大なデータの分析を通じて日本が「凡庸な教育格差社会」であることを論証した『教育格差:階層・地域・学歴』(ちくま新書、2019年)の著者・松岡亮二氏です。「Ⅰ 教育格差」「Ⅱ 『学力』と大学入試改革」「Ⅲ 教育政策は『凡庸な思いつき』でできている」「Ⅳ 少しでも明るい未来にするために」の4部から本書は構成されていますが、各部の各章は、そうそうたる顔ぶれの著者により簡潔ながらも「教育論の新常識」が高い密度でまとめられており、どれも必読です。
今回のブック・レビューで特に紹介したいのが、「データと研究に基づかない思いつきの教育政策議論」と題された末冨芳氏の論考です。これは「文部科学省(以下、文科省)の中央教育審議会(以下、中教審)を中心に、教育政策の意思決定におけるデータや研究の軽視およびその問題点をあきらかにしていく」(272頁)ために書かれた論考ですが、末冨氏が中教審のテーマ別部会(高校WG、教育課程部会)に委員として参加した経験に関するドキュメンタリーとしても読むことができます。末冨氏は、これらの部会に関わるなかで、以下のような「深刻な構造的課題」(274頁)が見えてきたと述べています。
●委員の多さと会議内での発言回数の少なさ、それによる議論の深まりのなさ。
●官邸・与党方針や幹部官僚の影響力もあり、担当官僚の政策方針に関する権限が限定されている場合もある。大半の政策課題については中教審等での意見書や議論、担当官僚とのコミュニケーションによる方針の改善が可能である。しかしイシュー次第では政官ルートでの交渉や報道等を通じた場外戦ともいえる問題発信がなければ、政策方針が転換しづらいケースもある(代表例として大学入試改革)。
●文科省のデータ収集・分析能力が十分ではなく、次に述べるように、教育委員会・学校現場や児童生徒に関する現状分析も不足する中で議論が進められてしまうこと。
●それにより、答申をはじめとする文科省の政策方針に対し、教育委員会や教職員をはじめとするステークホルダーからの信頼が低下し、またデータやエビデンスに照らし合わせても妥当性が低下してしまっていること。
3点目・4点目に係る例のひとつとして、高校WGにおける議論が「高校生になると授業以外の学習時間が短くなる傾向、そしてそれが中学校の時の成績と関連があり、成績下位層ほど高校になって勉強しなくなるという傾向」(277頁)を示すデータをもとに、「高校生が学習しないのはいまの高校教育は学習意欲を喚起するような魅力に乏しいからだというロジックがたてられ『特色・魅力ある教育を実現するために』スクールポリシーを作りましょう、という政策に帰結した」(同上)ことが紹介されています。
この政策について、末冨氏は「教育機会格差や子どもの貧困問題に関するアカデミックトレーニングを受けた読者なら、成績下位層ほど高校生になってから、困難な家庭環境に起因する可能性を想定した検証が行われるべきではないかと、疑問に思うはず」(同上)であると指摘します。なぜなら、「困難な家庭環境に育った高校生たちは、そもそも学習の意欲や習慣が高校入学までに十分形成されていなかったり、家計を支えるためのアルバイトに従事せざるを得なくなる」(同上)からです。そのうえで、以下のように末冨氏は述べます。
私自身は、大学と同様にスクールポリシーが形骸化し、スクールポリシーを作るために高校教員が多忙化し、高校生の学習時間にも教育の質にも大した効果はもたらさない、場合によっては高校生の学習意欲や学習時間にネガティブインパクトすらおよぼしかねないと危惧している。
スクールポリシーの形骸化に関し「大学と同様」と書かれていることをどのように受け止めるべきかについては、評価を担当する私にとって大変難しい問題です。本ブック・レビューでは大学の三つのポリシーの策定が広く言われるようになった起源等について検証する余裕はありませんが、大学における「三つのポリシーの実質化」を声高に叫ぶ前に、教育格差の問題、政策の立案過程、学生・教職員の現状(末冨氏は教育の現場を無視した改革は「よい成果にむすびつくことはない」(279頁)と指摘しています)等に視野を広げてみる必要があることは間違いないことであるように思われます。
この論考(ひいては本書全体)が示唆してくれるのは、認証評価を通じて大学・短期大学と直接対峙する認証評価機関は、政策の単なる旗振り役で終わるのではなしに、場合によっては大学・短期大学の防波堤となるべきだということです。換言すれば、認証評価機関として政策の内容を十分検討し、それが大学・短期大学に対してどのような影響を及ぼすことになるのか適切に吟味することこそが、今求められているのではないでしょうか。
もう1点、本書について記しておきたいのが、「あとがき」に記されている編著者である松岡氏の八面六臂の活躍です。「データで教育格差を含む実態を把握し、効果を出せる方法を追求し、知見を積み上げ政策と実践を微修正するサイクルを確立する」(353頁)ため、政策提言のみならず、「全国学力・学習状況調査」の改善、大規模なパネル調査の実施、教職課程で使用することを想定した「教育格差」の教科書の作成、当該教科書執筆者によるオムニバス授業の開催とその新書化、さらには単著の執筆と(354-362頁)、自らの知見と社会とをつなぐために尽力されていることに敬意を表さざるを得ません。
松岡氏の目指す実践が現実のものとなることを期待するとともに、私自身も何らかの形で貢献することができるよう、日々自問・実践していきたいと思わされた一冊でした。

